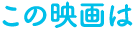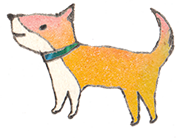MENU
MENU


「最近ね、散歩の途中でね、お猿さんがたくさん出てきて踊ってはるのよ……」
離れて暮らす母が電話口でいきなり突拍子もない事を言い出した。
「ほかにもね、鼻をビヨーンと伸ばした象もいるなぁと思って、近づくとね、岩なのよ。首の長いキリンもいるなぁとよく見ると、木なのよ」
いったい何の話デスカ?
「お父さんに言うと、またアホなことばかり言うてって叱られるから黙っているんだけどね……」
母は淡々と話すが、私はそりゃヘンだよ、お父さんじゃなくてもツッコムよ、とすかさずツッコミながらも動揺している。母はどうしちゃったのか? 動揺しつつも、道端で踊る猿と象とキリンを想像して声を上げて笑ってしまう。
それから約2カ月後。大学病院でのいくつかの検査の後、母には「レビー小体型認知症」の診断が下った。「幻視」や「錯視(見間違い)」は、このタイプの認知症の特徴だという。 「認知症」という病名には正直、うろたえた。他人事と思っていた介護生活が始まるのか? 介護認定などの手続きを進めていたしっかり者の父からも、ショックを受けているのがヒシヒシと伝わってくる。そして、何より母自身の不安を思うと胸が痛む。東京で映画制作という夢を追いかけている場合ではないのではないか。そんな思いを抱えながら、夏を過ごした。
だが、早くも秋口にはそんなに悲観的になることもない、という気がしてきた。幸いにも、母はかなりの初期段階で診断がつき、確実な投薬を続けているため、症状の進行を遅らせられているようだ。相変わらず、ヘンテコな幻視は現れているというが、それらを受け流す心持ちも獲得したらしい。母は今まで通りの母であろうとしている。日々の食卓の心配をし、家中に掃除機をかけ、几帳面に洗濯物を畳み、時折、父に対する愚痴をこぼす。
確かに、以前に比べると出来ないことが母には増えている。工程の多い料理であったり、細かい縫い物だったり。頼まれて、繕い物を引き受けた私の手元を、母は真剣な目で覗き込む。かつて子どもの頃の私がそうだったように。そうだ、母は少しずつ幼女に返っているのだ。私と立場が入れ替わる時期がきているのだ。
決して仲が悪かったわけではないけど、近寄りすぎると何かとメンドクサイ存在であった母親に対して、今までにない新しい気持ちが芽生えてきているのを自覚した。
SKIPシティ国際Dシネマ映画祭のオープニング作品募集を知る。書いてみようと思った。今しか書けない物語を。
深夜、真っ白のワープロ画面に向かった私の脳裏に突如、だだっ広い草原を走る犬のイメージが浮かんだ。そして、塊となって「物語」が降りてきた。もう若くもない娘が、母親の老いに直面し、向かい合うという物語が。
締め切りギリギリに提出したシナリオが選ばれたという知らせを受けた。『話す犬を、放す』が動き出した。
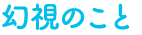
例えば「水道の蛇口から、小さな亀が出てきた」「玄関にエリザベス女王がお見えになった」などなど。見ている本人にとっては笑い事ではないだろうし、バカにする気など毛頭ないけれど、そこはかとないユーモアを感じてしまう。
同じ場所に居ながら、違うモノを見ていることを、なんとか映像で表現したいという私のこだわりに、撮影部を中心に試行錯誤が繰り返された。最終的に行き着いた「幻視」の表現が果たして正解なのかは誰にもわからない。なんせ幻視だから。
通常は見えないものが見えるというのは、どんな気分なんだろう? 娘レイコを演じるつみきみほさんがアドリブで発した「見てみたい」という言葉に、強く共感するばかりである。
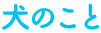
この物語の中で、犬はいろんなモノを象徴している。思いのほか、難航したのが「タイトルロール」でもある“話す犬”チロ役のキャスティングだった。
雄でも雌でも、白でも茶色でも黒でもいい。ただ唯一「雑種犬」という要望だったのだけど、動物プロダクション所属のタレント犬には「雑種」がなかなかいないらしい。そりゃそうか、CMやドラマに登場する犬は、たてがみを付けられても怒らない優しいゴールデンレトリバーや、お父さんみたいな北海道犬、可愛いプードルとかだよね……。でも絶対、昔、庭先の犬小屋で飼われていたような、和犬だか洋犬だかも判然としない、「雑種」でなきゃダメなんです、と言い張り、探してもらう。
そして、ようやく出会ったのが、めんまであった。茨城県まで逢いに行く。名前の通り薄茶色でスリムな体型の見るからに「THE雑種」の女の子、12歳。耳が横向きにピコンと立つのが超キュートである。一目で惚れ込んだ。これまでの出演歴を尋ねると「ヨゴシをかけて、野良犬役を何度か」とのこと(涙)。めんまにとって、今回は初めて名前とおうちがある役らしい。
犬の12歳は人間で言えば64歳くらいと聞いたプロデューサーが「走れるのか?」と心配していたけれど、それは失礼な話であった。めんまは本番ではNGを一度もだすことなく颯爽とした走りを披露してくれた。
物語に大きな躍動をもたらす、彼女のひたむきな疾走は、ひときわ印象的なシーンとなった。